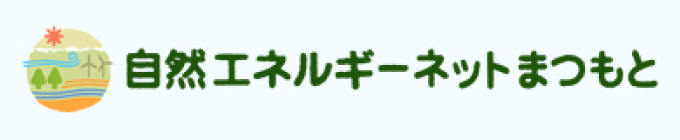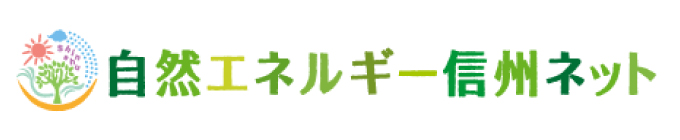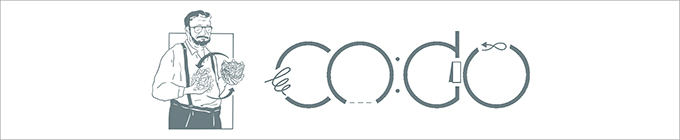2025年06月24日 編集長コラム
山里の田植えは、祈りからはじまった。
塩尻市片丘の山裾にある真言宗の寺「無量寺」の田植えに参加。長らく耕作していなかったお寺の田んぼを、急きょ有志で耕作・代かきをしてこの田植えとなった。私は、仏事(神事?)を伴う田植えと聞きお手伝いに伺うことに。
田植えの準備のできた田んぼの畦に、式台が用意され、最初に無量寺の住職の念仏、そして法螺貝が響く神事が行われ、大地と自然と山々の神に稲作の無事を祈った。


田植えの終わりも、法螺貝の響きで締めくくられた。日本の稲作文化の「祈り」を体感できた、有意義な時間だった。
人と自然の関わり方には、大きく次の4つがあるとIPBES事務局長のラリゴーデリー博士はいう。
- Living from Nature(自然によって生きる)
食料や生活用品など、人が生活を営み、必要とし、望むものを提供する源泉である自然の力が重要だと考える。 - Living with Nature(自然と共に生きる)
人間以外の生物、例えば川に住む魚が、人間が必要としているかどうかとは無関係に繁栄する権利がある。人間も他の生き物も同等に生物多様性を構成するメンバーだ。 - Living in Nature(自然の中で生きる)
人の居場所や暮らしや文化にとって、自然は重要な場所である。 - Living as Nature(自然として生きる)
自然界を自分自身の肉体的、精神的な一部と考える。人間も自然界の一部分だ。
人間社会にとって、Living from Nature(自然によって生きる)の考えが中心だが、今回の田植えは、まさに日本人の中に息づくLiving as Nature(自然として生きる)を感じることができる体験だった。