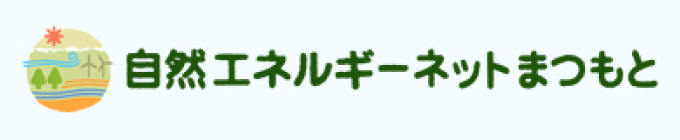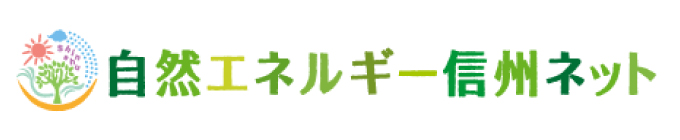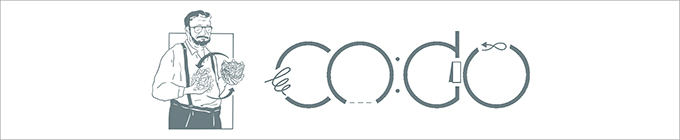2025年11月07日 経済・社会・教育
自分を健康に導いてくれた味噌の魅力を岡谷から。創業93年の老舗味噌蔵5代目の挑戦

豊富な水源と澄んだ空気、味噌づくりに欠かせない豊かな自然に恵まれた長野県。信州味噌は古くから県内のみならず首都圏をはじめとする日本中に出荷され、現在もそのシェアは全国の約半数、生産量は日本一を誇ります。
中でも、諏訪・岡谷地域は味噌蔵が多いエリアで、日本の味噌づくりの技術力向上に貢献してきたそうです。岡谷市には今も9つの味噌蔵がそれぞれに個性豊かなこだわりの味噌をつくり続けています。
今回、お話を伺ったのは岡谷市の味噌蔵のうちの一つ、喜多屋醸造店の5代目代表取締役社長 長峰 愛さんです。喜多屋醸造店の長女として、2025年6月に代表取締役に就任、次女の白鳥 彩さん(専務)とともに、日々味噌づくりと会社経営に奮闘されています。
90年以上もの歴史をもつ家業を継ぐに至った経緯、愛さん自身が世界有数の発酵食品で万能調味料でもある味噌に魅了され続けているわけ、そして地元や味噌づくりへの想いなどを、芳しい味噌の香りがほんのり漂う工場併設直売所の一角で、たっぷりとお話いただきました。

◎長峰 愛さん
有限会社 喜多屋醸造店の代表取締役社長。会社の顔として主に広報活動に取り組む。幼い頃から料理好きで、味噌愛は誰にも負けない。調理師免許、みそソムリエ、野菜ソムリエ、ナチュラルフードアドバイザー、味噌製造技能士2級。
きっかけは、自身の体調不良。食の大切さを身をもって体験
幼い頃から料理が好きで、調理師免許のほかにみそソムリエの資格も持ち、自社の商品だけでなく、味噌そのものの魅力を発信し続けている愛さん。自他ともに認める無類の味噌好きだといいますが、これほどまでに味噌に魅了された訳には、自身の経験がありました。
「高校を卒業後、調理師免許の資格を取る勉強をするために上京し一人暮らしを始めました。その頃のわたしは食への探究心から、テレビで話題のものからミシュランの星付きレストラン、コンビニ食にお惣菜など、あらゆるものを自由に食べていました。専門学校を卒業してからは東京の飲食店に就職したのですが、自由な食生活がたたって少しずつ体調を崩し、仕事ができなくなってしまったんです」

身体がだるくなり、それは心にも影響し、何をするにもやる気が出なくなってしまったという愛さん。最終的には摂食障害になり、吐いてでも食べ続けるという深刻な状態に。
なんとか自分を変えたい、変えなければならないという切実な想いから、自分の身体に向き合った結果、改めてたどり着いたのが「わたしたちの身体は食べたものでできている」という食の大切さでした。
それからというもの、自炊を増やし、食品添加物を控えてできるだけ野菜をたくさん摂るよう食生活を一変。すると徐々に体調は回復し、心身ともに元気になっていきました。
三食きちんと自炊をすることが大変ななかで、有機野菜と喜多屋醸造店の味噌を使った一汁一菜の食生活によって体調は回復してきます。幼い頃から実家では当たり前のように毎日食べていた味噌汁。「栄養の宝庫」と称される味噌なので具沢山にすれば一杯であらゆる栄養素を摂ることができ、アレンジの可能性が多彩で飽きることがない。味噌汁は弱っていた愛さんの心と身体にエネルギーをくれました。
自分の家でつくっている味噌のおいしさに気づき、味噌への探究心に火がつく
実家でつくっている味噌のおいしさを実感し、体調は回復しましたが、新しい就職先の飲食店で人間関係に悩んでいた20代中盤。
「ある日、何の連絡もなく父が店にお客さんとしてやって来てくれたんです。“いつでも帰ってこい”という言葉にとても励まされました。その頃は実家でつくっている味噌のおいしさを実感していましたし、父にも恩返しをしたいと思いました」。
それをきっかけに、愛さんは、青山ファーマーズマーケット(※)で喜多屋醸造店の味噌を売り始めます。
※青山ファーマーズマーケットとは
生産者と都市の消費者を繋ぐ場として、生産者に販売機会を、消費者に新鮮な食材を手に入れる機会を提供することを目的に、2000年代後半に、青山の国連大学前の広場を拠点にスタート。オープン当初は5店舗からのスタートでしたが、現在では80軒近くが出店し、毎週末に開催され1万人(1日)以上が訪れる人気の大規模マーケットへと成長した。

知れば知るほど、味噌の魅力にどっぷりと浸っていき、いつしかみそソムリエの資格も取得。ファーマーズマーケットを通して、野菜や食品の生産者とつながる機会が増えたことにより、無農薬野菜や有機農業などへの関心も深まっていきました。
ところが同時に、家業が味噌屋でありながら、自分が味噌について何も知らないことに気がつきます。この頃の愛さんの夢は料理研究家として、味噌の魅力を広めること。夢の実現に向けて味噌についてもっと学びたいという気持ちが高まり、実家である喜多屋醸造店に“修行”に帰ってきたのが、2012年のことです。

3年間限定の修行のつもりが、姉妹で老舗の5代目に
「もともと、修行は3年間限定のつもりで、家業を継ぐというつもりはなかったんです。家族も長男である弟が継ぐと思っていましたね」
姉妹二人三脚で経営に励む現在の姿からは意外な当時の気持ちを語ってくれた愛さん。喜多屋醸造店に戻ってきてから数年後、改めて後継ぎをどうするかという家族会議になり、諸事情から弟さんが継がないということが決まってからはじめて、愛さん、そして妹の彩さんの二人に家業を継ぐという選択肢が生まれました。
幼い頃は、父親の麹を仕込む作業を手伝うのが楽しみだったという。お手伝いでできることといったら、固まった麹をほぐすことくらいだった幼少期の愛さんにとって、麹のいい香りが漂う蔵はとっても特別な場所でした。
●昭和40年代に起こった2回の火事で工場が全焼。残ったのは、レンガ築炉ボイラーのみ
昭和7年(1932年)から続く味噌づくりですが、昭和40年代に存続の危機が2回ありました。相次ぐ2度の火事で工場が全焼。ただ、レンガ築炉ボイラー(※)だけは、2度とも奇跡的に無事でした。
当時3代目だった祖父が「ボイラーが残っているなら続けられる」と、気丈に奮闘し再建された喜多屋醸造店です。



そんな苦難を乗り越え代々受け継がれてきた喜多屋の看板と味噌の味を守りたい。なくなってしまうのは嫌だ…その想いは妹の彩さんもいっしょで、姉妹二人で5代目を継ぐことを決心します。
「会計事務所に勤めていた妹の彩に“味噌に対する想いはお姉ちゃんが持っているから大丈夫。経営の部分は自分ができるから”と言ってもらって、それが本当に頼もしかったです。社長はわたしですが本当に二人で継いだという感じですね」。

健康とおいしさ、そして自然な素材にとことん向き合って生まれた有機米みそ「しぜんと。」
家業を継ぐことを決意したのは、愛さんが長女をおなかに宿していた頃でした。現在は2児の母親として育児にも奮闘されています。母親になったことで、自然農法や有機栽培への関心はより深まり、味噌づくりにおいても新たな挑戦に踏み出しました。それが、オーガニック(有機)味噌づくりです。
完全有機での味噌づくり、そしてそれをビジネスとして成立させることの難しさを知るからこそ、最初は反対していた4代目の父親(現会長)も、10年以上有機農業と関わってきた愛さんの熱意を受け止め、「やる覚悟があるなら、やってみろ」とチャレンジの場を与えてくれました。
「有機農産物は私を元気にしてくれたもの。そして、子どもたちが育っていく未来の環境を考えると、持続可能な農業でもある有機農業を続けている農家さんを応援したい。そんな環境をつくっていきたい。という思いが大きかったです」。

有機の味噌づくりは、有機JAS認証を取得している信頼できる原材料の確保が重要です。長野県松川村で20年以上有機農業に取り組む「宮田農園(※1)」の宮田兼任さんと宮田さんと一緒に取り組んでこられた故・矢口一成さんから、有機JAS認定のお米と大豆を分けてもらうことで有機の味噌づくりは始まりました。現在は、宮田さんの弟子でもある「北アルプス高橋農園(※2)」の高橋克弥さん、そして小布施町のオーガニック福祉農園「社会福祉法人くりのみ園(※3)」さんからもお米と大豆を提供してもらっているそうです。
こだわりをもって安心な農産物をつくっている長野県内の生産者さん一人一人に、愛さんたちの思いを伝えながら仕入れ先を確保しています。
「農薬・化学肥料などを使わずに栽培している農家さんの中で、 この方々だったら安心して任せられるという方々と取引させていただいているのは、わたしたちの強みであり、自慢ですね。宮田農園の宮田さんも、北アルプス高橋農園の高橋さんも、わたしたちの想いに共感してくださって、お力添えいただき本当にありがたいです」。

※1「宮田農園」の宮田兼任さん
20年以上前から化学的な農薬を使った近代農業に危機感を抱き、有機農業にいち早く取り組む。現在、松川村と池田町で学校給食に有機のお米を提供することに力を入れて、有機JASの農家を増やすため、まわりの農家さんたちに有機の生産技術を伝える活動に取り組んでいる。
*2「北アルプス高橋農園」の高橋克弥さん
高橋さんは、世界中を旅する中で、日本の発酵食品は日本の宝だと感じ、一方で原材料を見るとほとんど海外からの輸入であるということにショックを受け、作り手がいないなら自分がやろう!と、有機農業の道に。「自分のお米と大豆で味噌を作ってほしいと思っていた」高橋さんと喜多屋の愛さんの思いがぴったりとリンクした。
※3「社会福祉法人 くりのみ園」
くりのみ園さんはオーガニックの福祉農園です。平飼い養鶏と自然循環農法で、地域農業に貢献。令和2年(2020年)の有機JAS認証取得。人も持続可能な農業を目指し、障がい者就労支援をしている。
●有機JAS認証のポイント
◎農薬・化学肥料に頼らない生産
堆肥による土づくりを基本とし、化学合成された農薬や肥料を一定期間使用しないことが求められる。
◎遺伝子組換えでない種子
遺伝子組み換えの種子、菌、苗を使用しないことが原則。
◎第三者機関による審査
登録された「登録認証機関」が、書類審査や実地調査を行い、基準に適合しているかを確認する。
◎継続的な管理
認証後も、約1年に1回の年次調査を受け続けなければ、認証事業者として継続できない。
◎表示のルール
有機JASマークのない農産物や加工食品に、「有機」「オーガニック」といった紛らわしい表示をすることは法律で禁止されている。

有機JAS認証の工場は大変!混ぜ物、数、製造ラインも厳しくチェック。有機の味噌づくりのもう一つの関門
有機JAS認証の米や大豆を使っているだけでは、有機の味噌はつくれません。有機JAS認証を取得した生産現場がなくては商品にならないのです。有機原料以外が混在・混入しない加工現場の実現と商品の数量などの管理体制等、第三者の登録認証機関による、現場調査や厳重な書類審査が毎年繰り返されます。
立ち上げも継続も想像以上に大変だったと話す愛さん。ただ、苦労と引き換えに、安全と信頼は継続されていきます。

こうして、さまざまな人の協力と生産現場の努力から信州産有機米みそ「しぜんと。」が2年前に誕生しました。なめらかな舌触りとやさしい甘味の「ひなた」、熟成された旨味に力強さを感じる「大地」。限りなく自然に近い環境で育った米や大豆のエネルギーが凝縮されていて、食べればそのまま身体に染み渡る、まっすぐな味噌です。
「値段も張るので、そう売れるものではないですが、京都や大阪からの注文もあり、全国に求めている方がたくさんいらっしゃるという実感はあります。それに、「大地」の発売に際して、皆さんに認知してもらう効果も考えクラウドファンディングに挑戦しました。30万からのスタートでしたが、最終的には180万円が集まりました。応援してもらえている実感がとても嬉しかったです」。

無農薬・無肥料の自然農栽培(自然栽培)原料の味噌づくりに挑む
茅野市で自然農を営む東城高太郎さん(※)がつくる農薬はもちろん肥料も使わず、太陽と水と土(土壌生物)の恵によって植物本来の力で育った大豆とお米に出会い、その自然で力強い生命力とおいしさに感動した愛さん。これを、味噌にして皆さんに届けたいという思いが「しぜんと。八ヶ岳の自然栽培みそ」を誕生させました。
力のあるお米と大豆に負けないように、塩もこだわりの製法でつくられた「石垣の塩」を使用し、一年以上木桶に寝かせて完成します。
「こだわりを詰め込んだので、値段もかなり張りますが、少量仕込みで、限定販売なので、今年の販売分は完売です。今は、2026年の秋頃の発売に向けて木桶の中で熟成中なんです。味見していただけなくて残念です」。


※「自然栽培農家」東城高太郎さん
茅野市に生まれ、一度故郷を出て就職したが、土にふれる生き方がしたくてUターン。慣行農法のあり方に違和感を感じていた時に、自然農法の存在を知る。自然のサイクルに沿って、余計なものは加えずに育った作物のおいしさに感動し、自然農での農業を営むようになる。手づくりにこだわった暮らしを実践し、その素晴らしさを提唱している。

地元を味噌で盛り上げたい。岡谷を味噌の観光名所に
喜多屋醸造店では、30年以上前から学校給食に味噌を卸しています。現在、岡谷市、辰野町、箕輪町の学校給食の味噌は、喜多屋醸造店のものを使っているそうです。また、地域の未来を担う子どもたちに味噌の素晴らしさを伝える食育の取り組みにも力を入れています。他の味噌蔵とも協力して岡谷市内のほとんどの保育園(岡谷市内の保育園は全園で味噌づくりを実施)、小学校、中学校で味噌づくりの体験やワークショップを開催しているというから驚きです。
「子どもたちにとって、今はまだ、地元にこうして味噌蔵が残っていることの価値がピンと来なかったとしても、彼らが成長して大人になったときに、いつかすごいことだったんだってきっと気づいてくれると思うんです。だから、伝えることはずっと続けていきたいですね」。


愛さんが代表取締役社長に就任して4か月。最後に、これから挑戦していきたいことを伺うと、地域への想いを語ってくれました。
「 信州味噌という大きなブランドがあるから、地域ごとでの味噌の差別化が難しいですし、県内は競合ばかりで、正直なところなかなか大変です。でも、長野県産にこだわっている原材料で、良いものをつくっているという自負をもっと高めて、おいしい地元の味噌を地域の方々に広く知ってもらいたい。岡谷を味噌の観光名所にすることは成し遂げたいと思っています」。
“わたしたちの身体は食べたものでできている”
からこそ、未来に向けて「食の大切さ」を多くの人に伝えることは大事な取り組みです。日本の伝統的な健康食品「味噌」を通して、熱量をもってそのことを伝えている長峰 愛さん・白鳥 彩さんの取り組みが、地域に変化を起こしつつあります。
創業93年目、喜多屋醸造店5代目の挑戦は始まったばかりです。
姉妹のアクションから目が離せません。